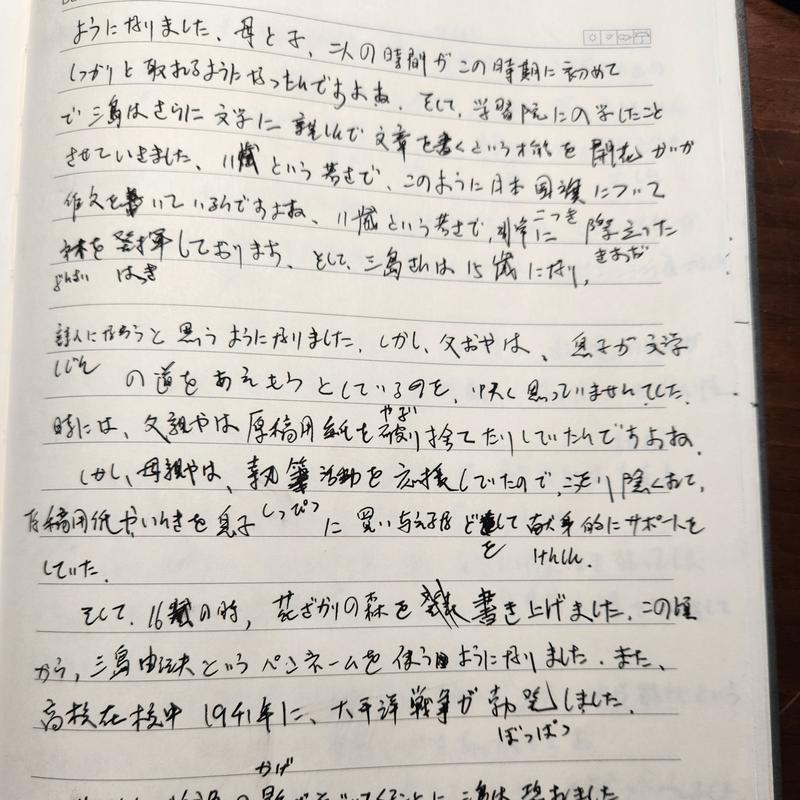www.soumu.go.jp
「選挙」は、私たち一人ひとりのために。
私たちは、家族や地域、学校や職場など、さまざまな場でくらしています。私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。
1. みんなの代表
選挙によって選ばれた代表者は、国民や住民の代表者となります。したがって、その代表者が職務を行うに当たっては、一部の代表としてではなく、すべての国民や住民のために政治を行うことになります。
2. 多数決
民主政治の原則である多数決は、人々の意見を集約(しゅうやく)し、決定する際に用いる方法です。より多くの支持を得た者を代表者とすることによって、政治の安定化を図ります。
3. 「身近」「みぢか」な選挙
「選挙」とは、私たちの代表を選び私たちの意見を政治に反映させるためのもの。そのためにも、私たち一人ひとりが「選挙」に関心を寄せることで、「選挙」はもっと身近なものになるといえます。
4. 憲法と選挙
選挙に関する規定を定めた公職選挙法は、日本国憲法第15条で明記されている「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という憲法の精神にのっとっています。
5. 選挙と政治
日本は国民が主権しゅけんを持つ民主主義国家です。選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。
6. 政治と国民
「人民の、人民による、人民のための政治(政府)」。民主主義の基本であるこの言葉は、私たちと政治との関係を象徴しょうちょうする言葉です。
国民が正当に選挙を通してとおして自分たちの代表者を選び、その代表者によって政治が行われます。
選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出て、みんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
1. 選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
2. 被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くつくことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
「選挙」は、大きく2つの分類に分けられます。ひとつは、どんな公職の人を選ぶかという分類です。国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員など、選ぶ対象が定められています。もうひとつは、「選挙」を行うべき理由(選挙事由)での分類です。任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。
1.衆議院議員総選挙
総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
その中、比例代表の***選挙区は11ブロックで、合わせて、***176人の席が設置しました。
具体的には、
北海道 北海道8 (ほっかいどう ほっかいどう はち)
東北 青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島12 (とうほく あおもり/いわて/みやぎ/あきた/やまがた/ふくしま じゅうに)
北関東 茨城/栃木/群馬/埼玉19 (きたかんとう いばらき/とちぎ/ぐんま/さいたま じゅうく)
南関東 千葉/神奈川/山梨23 (みなみかんとう ちば/かながわ/やまなし にじゅうさん)
東京都 東京19 (とうきょうと とうきょう じゅうく)
北陸信越 新潟/富山/石川/福井/長野10 (ほくりくしんえつ にいがた/とやま/いしかわ/ふくい/ながの じゅう)
東海 岐阜/静岡/愛知/三重21 (とうかい ぎふ/しずおか/あいち/みえ にじゅういち)
近畿 滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山28 (きんき しが/きょうと/おおさか/ひょうご/なら/わかやま にじゅうはち)
中国 鳥取/島根/岡山/広島/山口10 (ちゅうごく とっとり/しまね/おかやま/ひろしま/やまぐち じゅう)
四国 徳島/香川/愛媛/高知6 (しこく とくしま/かがわ/えひめ/こうち ろく)
九州 福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄20 (きゅうしゅう ふくおか/さが/ながさき/くまもと/おおいた/みやざき/かごしま/おきなわ にじゅう)
2.参議院議員通常選挙
参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。参議院議員の定数は248人で、うち100人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出議員です。
3. 一般の選挙(地方選挙)
一般選挙(地方の議会) 一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。
地方公共団体の長の選挙 都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(せいきゅう)(リコール)による解職(かいしょく)
や、不信任議決(ぎけつ)による失職、死亡、退職、被選挙権(ひせんきょけん)の喪失による失職の場合などにも行われます。
設置選挙 新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。
※統一地方選挙 地方公共団体の長と議会の議員の選挙を、全国的に期日(きじ)を統一(とういつ)して行う選挙を統一地方選挙といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また、選挙の円滑かつ効率的な執行(しっこう)
を図る(はかる)目的で、昭和22年からこれまで4年ごとに行われてきました。
4. 特別の選挙(国政/地方選挙)
再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を「補う」「おぎなう」) 選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも「繰上」「くりあげ」当選(繰り上げる場合がある)などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
補欠選挙(議員の不足を補う) 選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。※国の選挙の場合、原則として、補欠選挙は年2回、4月および10月の第4日曜日に行われます。
**増員選挙(議員の数を増やす)**議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。※地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる6カ月以内に当該選挙を行うべき事由(じゆう)が生じた場合には議員の数が定員の3分の2に達しなくなったときを除いて、行わないこととされています。
立候補
公職選挙法は、立候補の届出をした者でなければ、有効に当選人となることができないとする立候補制度をとっています。
1.立候補の届出
選挙に立候補するには、「立候補の届出」をする必要があります。国の選挙や地方公共団体の選挙への立候補の届出には、次の3つの方法があります。
- (1) 政党届出衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙および参議院比例代表選挙で行うことができます。一定の要件を満たす政党その他の政治団体が、選挙長に届け出ます。比例代表選挙の場合は、「候補者名簿「めいぼ」」を届け出ることになります。
- (2) 本人届出衆議院比例代表選挙・参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。候補者になろうとする本人が、選挙長に届け出ます。なお、代理人による届出もできます。
- (3) 推薦届出衆議院比例代表選挙・参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の「許諾」 「きょだく」 を得て、この人を候補者にしたいと、選挙長に届け出ます。
2.通称使用の申請
立候補届には本名(戸籍上こせきじょうの氏名)を記載しますが、本名以外で広く通用している通称がある場合、立候補届と同時に「通称つうしょう使用の申請しんせい」をして、申請が認められれば、立候補者名の告示こうじ、選挙公報こうほうの氏名、政見せいけん放送の氏名などに通称が使用できます。通称使用が認められた場合でも、候補者が選挙運動の中で本名を使用するのは自由ですし、投票の際に有権者が本名を書いても投票は有効です。また、本名を仮名かめい書きにする場合も通称使用の申請をする必要があります。
3.立候補の届出期間
立候補の届出期間は、選挙の期日の公示または告示があった日の1日間だけです。また、受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。
4.立候補の辞退等
いったん立候補した後に立候補を辞退できるのは、立候補の届出期間中に限られています。立候補の辞退は文書で選挙長に届け出なければなりません。衆議院・参議院の比例代表選挙では、選挙の期日の10日前までの間に文書で選挙長に届け出れば、政党等は名簿を取り下げることができます。
5.政党等の要件
候補者の「政党届出」をする政党等は、その選挙について、以下に挙げる要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
6.供託
立候補の届出では、すべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書こくさいしょうしょを法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」きょうたくといいます。供託は、当選を争う意思いしのない人が売名(ばいめい)などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。ですから、その候補者や政党等の得票数とくひょうすうが規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託された現金や国債証書は全額(衆議院・参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収ぼっしゅうされ、国や都道府県、市区町村に納められます。おさめる。
7.立候補の禁止と制限
被選挙権を持っていない人の立候補は禁止されています。また、被選挙権があっても立候補を制限される場合があります。例えば「重複立候補(※1)」、「連座制(れんざせい)(※2)による立候補禁止」などの場合です。
8.立候補届の受理
選挙長は、立候補届の記載と添付書類に問題がなければこれを正式に受理します。届出の受理の順番は受付場所への到着順ですが、受付開始時間前に到着した者の間の順番は、公平を期すためくじ引きで決めます。
9.候補者の異動
立候補届が受理じゅりされた後、候補者に異動が起こることがあります。たとえば、その後の調査で被選挙権がないとわかった場合や、不幸ふこうにも死亡された場合などです。この時は立候補届の却下きゃっか、候補者名簿からの抹消(まっしょう)が行われ、場合によっては補充的な立候補の受付などが行われます。
「補充的」の発音は、「ほじゅうてき」です。
空空如也
暂无小宇宙热门评论